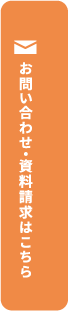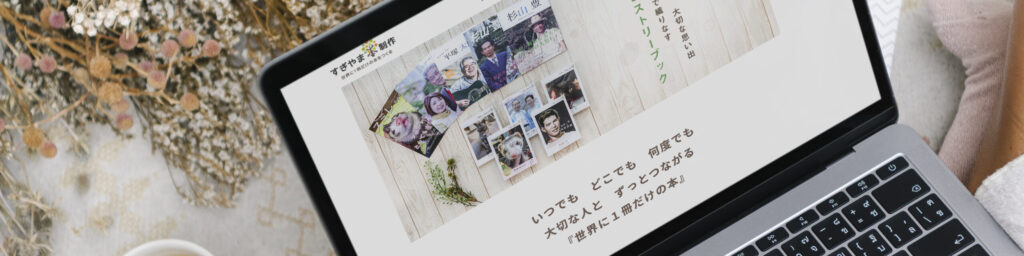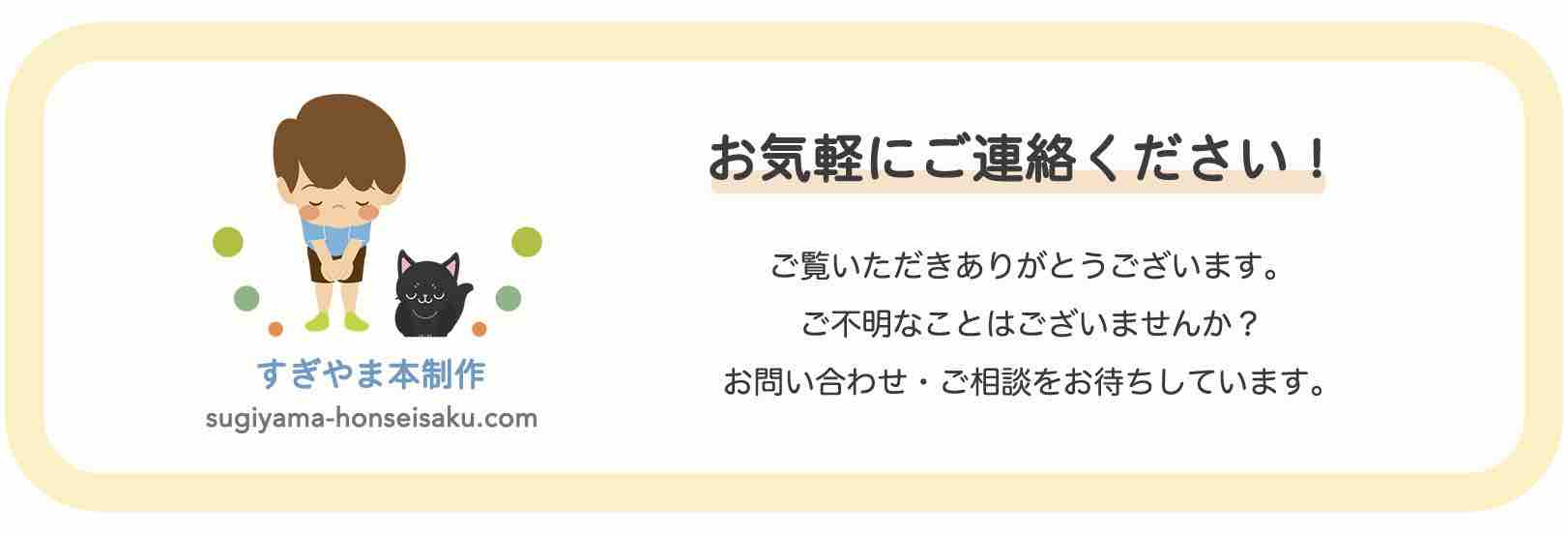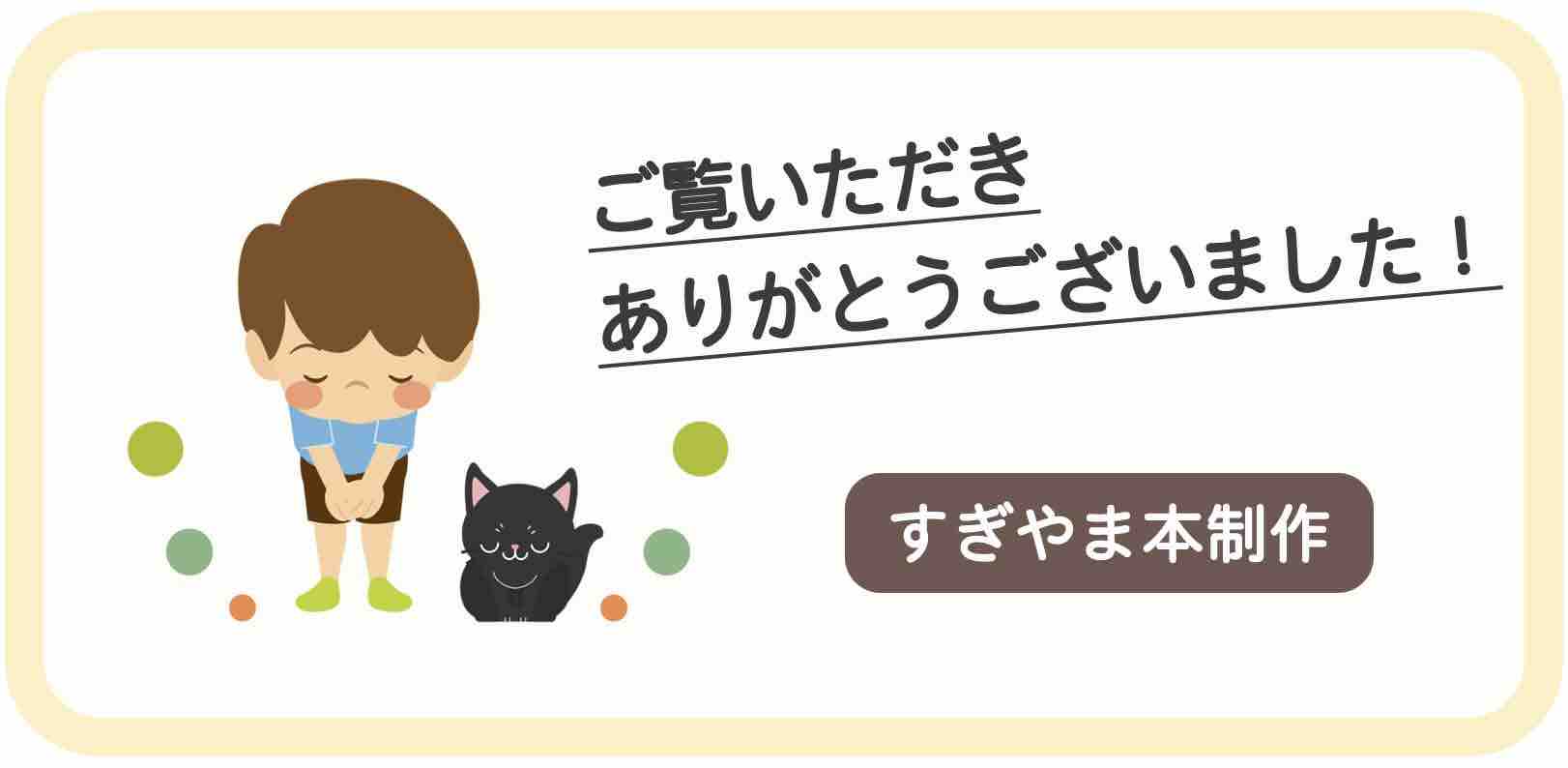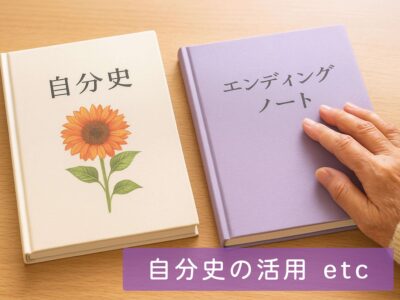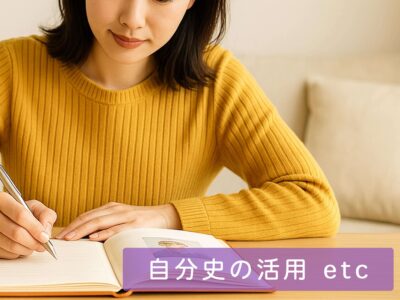2025.09.26
教育現場での自分史活用|授業・キャリア教育・地域連携の効果

このページでわかること
自分史は授業・キャリア教育・地域連携でどう活かせる?
本記事では、授業アイデア/進め方/評価の観点/地域との連携方法を具体的に解説します。
生徒の自己肯定感や表現力、コミュニケーション力を伸ばし、探究的な学びにも直結します。
授業での活用アイデア
自分史は、国語・社会・総合的な学習の時間など、多教科と親和性があります。
小テーマを設定し、短いサイクルで成果物(自分史)を作ると進めやすいです。
☝️ 国語×自分史
作文(思い出の一場面)/インタビューの要約/構成・推敲の学習
☝️ 社会・歴史
家族史と年表づくり/地域史と重ねる調べ学習
☝️ 総合学習
写真・資料収集 → 編集 → 発表の「自分史プロジェクト」
☝️ ICT活用
スライド・動画・音声で発表(紙の冊子と併用など)

「一枚の写真から書く」「10の質問で聞く」など、切り口を限定すると生徒が手を動かしやすくなります。
キャリア教育への効果
過去→現在→未来をつなげる自分史は、自己理解を深め、将来設計の土台になります。
履歴書(志望理由)や面接時の自己紹介・自己表現にも繋がります。
☝️ 自分の強み・価値観を言語化(成功体験・悔しさ・影響を受けた人など)
☝️ できごと→学び→行動のフレームでストーリー化(STAR法の練習にも)
☝️ ポートフォリオ化(スライド/冊子)で成果を見える化
地域とつながる自分史学習
地域の方へのインタビューは、世代間の交流と郷土(地元)の理解を促します。
安全管理に努め、聞き取った情報の取り扱いに注意しましょう。
☝️ 連携例
地域の高齢者、経営者や商店主・職人さんの自分史を聞き取りをして、教室などで整理して記事化し、展示会などで発表する
☝️ 効果
「生きた歴史資料」が集まり、地域の記録アーカイブづくりにも貢献できます
進め方(3〜6時間でミニ実践)
STEP1:テーマ決め(生い立ち/家族/学校生活/地域など)
STEP2:素材集め(写真1〜3枚・思い出メモ・取材メモ)
STEP3:文章化(見出し→本文200〜600字)+年表ミニ版
STEP4:編集・レイアウト(紙面 or スライド)
STEP5:発表・相互コメント(良い点を具体的に伝える)
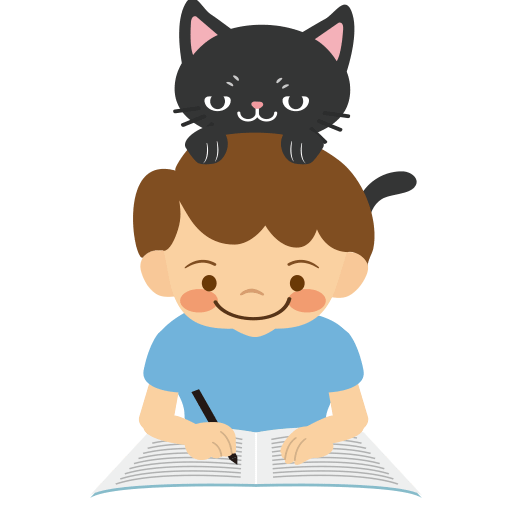
写真が用意できない生徒は「記憶スケッチ」などでもOK。
一人ひとりに配慮しながら、全員が参加できる仕組みを作りましょう。
評価の観点(ルーブリック例)
☝️ 内容:出来事→学びの掘り起こし→今後に繋がっていく
☝️ 表現:見出しや文章・写真キャプション・構成が読みやすい
☝️ 協働:取材マナーやルールの遵守・相互コメントが適切
よくあるご質問
Q:個人情報はどう配慮する?
→ 公開範囲を明確化し、顔写真や実名は同意を得て使用すること。展示会などをする場合は、参加者や公開範囲を限定するなど。
Q:時間が足りない場合は?
→ 1テーマ1ページの「ミニ自分史(1枚の自分史)」を作成し、夏休みや学期末にまとめる方法も良いでしょう。
Q:家庭の事情で書きにくい生徒は?
→ 「地域の人の自分史取材」「尊敬する人のミニ伝記」など代替課題を用意しても良いです。
最後に・・・
自分史は、生徒の「過去・現在・未来」を結び、主体性や人間理解を育てる学びの1つになります。
学校行事や地域イベントとも相性が良いので、小さく始めて継続し、クラス・生徒の学びや思い出を増やして見てはいかがでしょうか?