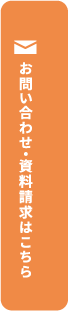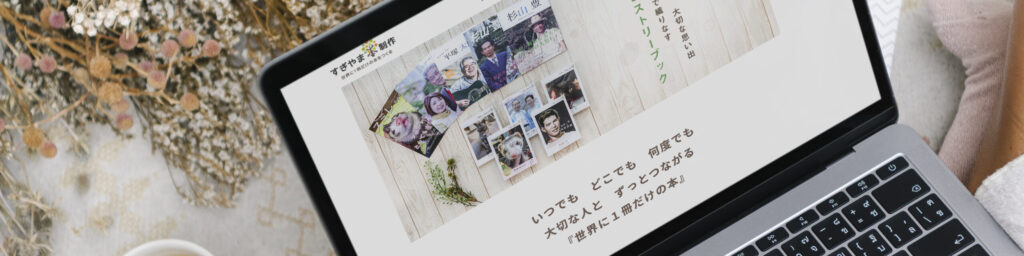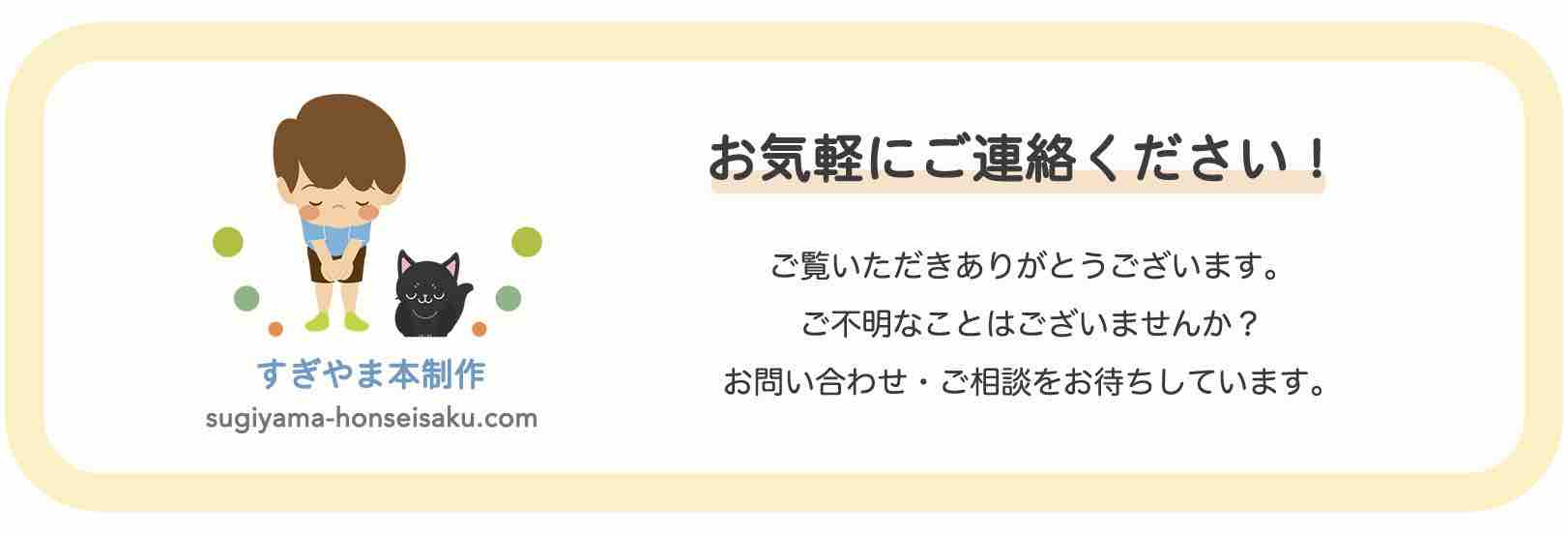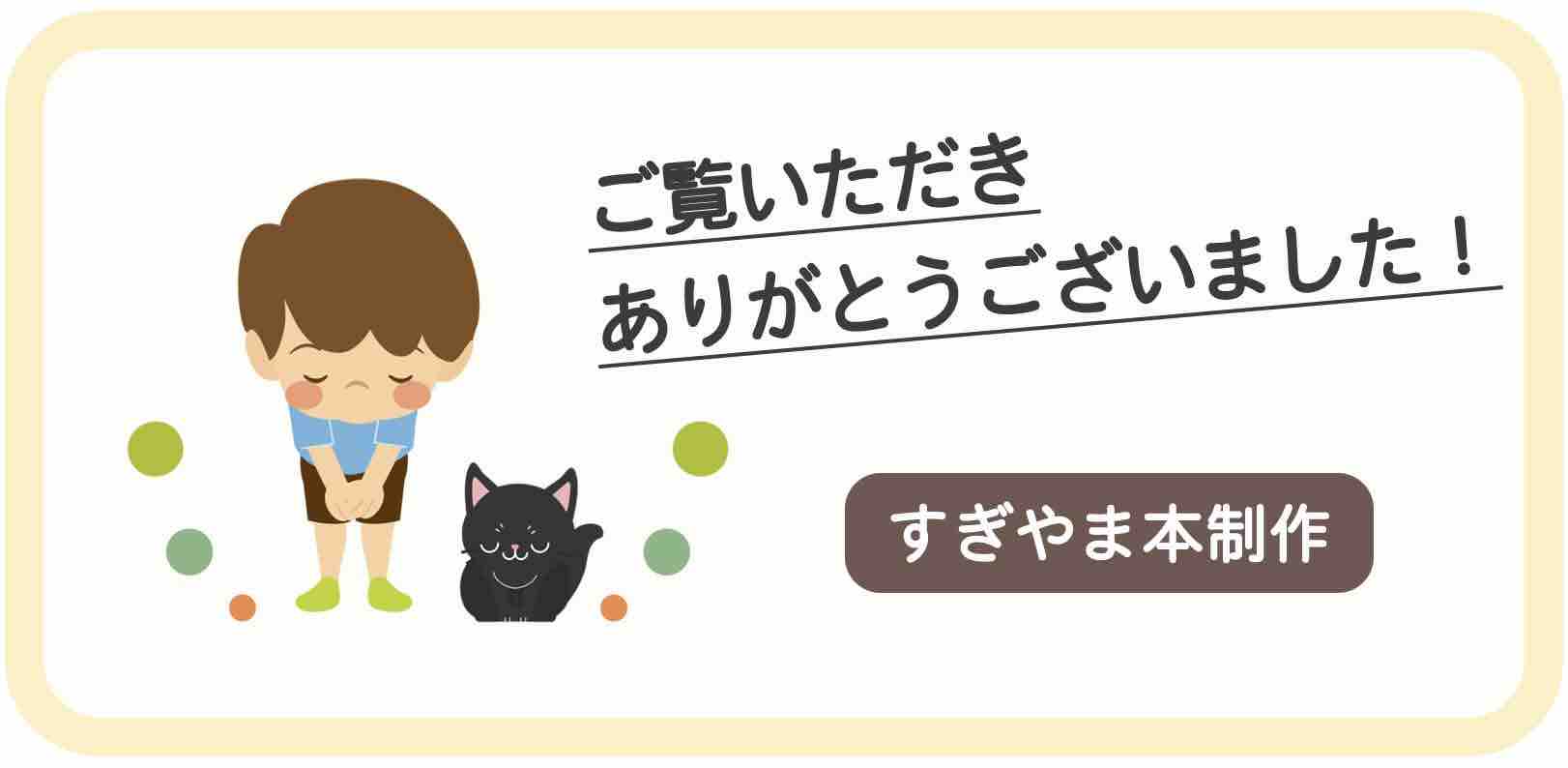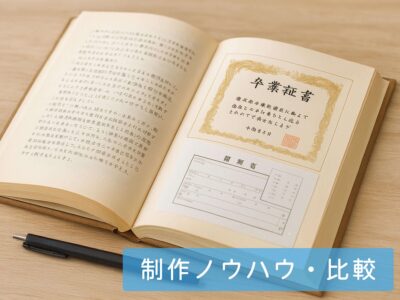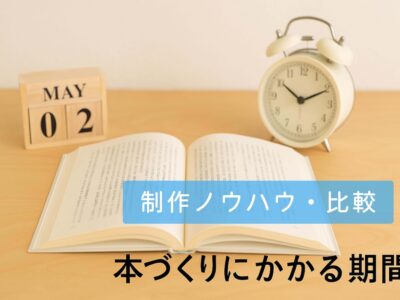2025.09.26
自分史の作り方比較|本・映像・デジタルの違いと選び方
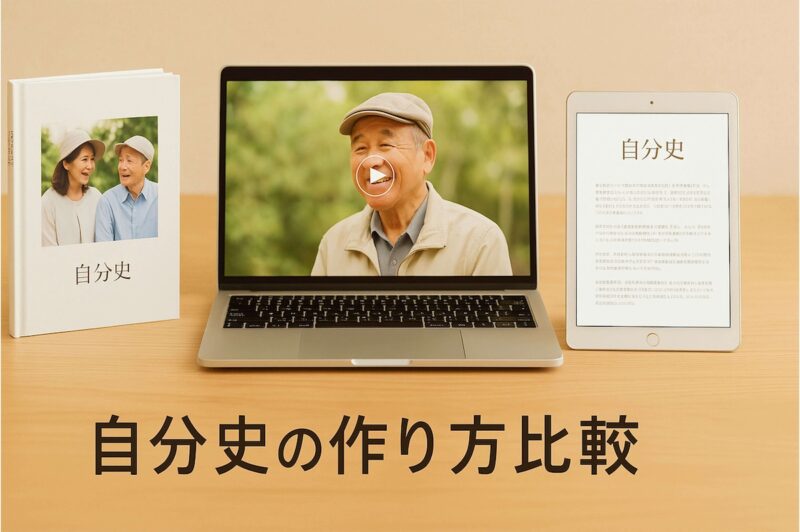
このページでわかること
「自分史を残したいけれど、どの形が最適?」
そんなお悩みにお応えするため、本/映像/デジタルの3タイプを比較し、選び方のコツをまとめました。
読み返しやすさ、共有のしやすさ、費用や保存性などを丁寧に整理。ご自身やご家族に合う自分史の形が見つかります。
このページでは、3タイプの特徴・おすすめの人・選び方の流れをわかりやすく解説していきます。
自分史の3タイプとは?(本/映像/デジタル)
自分史は大きく「本(書籍)」「映像(動画)」「デジタル(Web・データ)」の3つのタイプに分けられます。
目的や家族構成、贈る(共有する)相手によっても、最適解は異なります。
☝️ 本:読み返しやすく、贈り物や長期保存に強い
☝️ 映像:声・表情・空気感まで残せて臨場感がある
☝️ デジタル:共有が簡単、遠方の家族とも見られる、更新しやすい
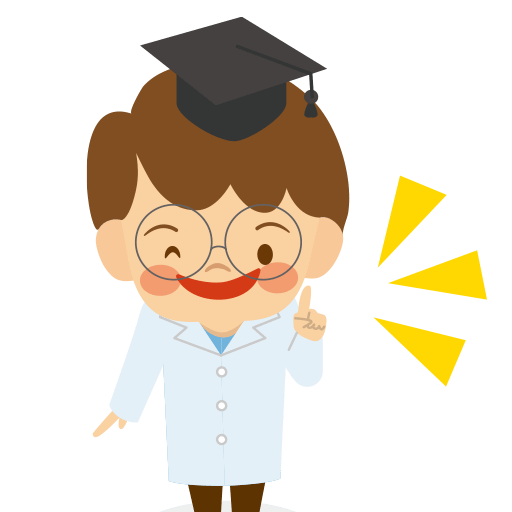
「誰に・どんな場面で・どう使いたいか」から逆算すると失敗しません。
選び方の流れ(3タイプ共通の判断ステップ)
共通で使える、自分史づくりのための、迷わない基本フローです。
※複数タイプの組み合わせ(例:本+デジタル)も有効です。
① 利用シーンを決める
家族で読み返す/贈り物にする/法要・学校・地域で共有する など。
② 残したい要素を整理
写真中心・文章中心・声や表情・資料(手紙・賞状) など。
③ 保管・共有の方法を選ぶ
紙で残す(本)、上映したい(映像)、遠方と共有(デジタル) など。
④ ざっくり予算と期間を把握
本は編集〜校正、映像は撮影・編集、デジタルは運用性がポイント。
⑤ 組み合わせを検討
本+PDFデータ/本+映像/デジタル+抜粋冊子 など。
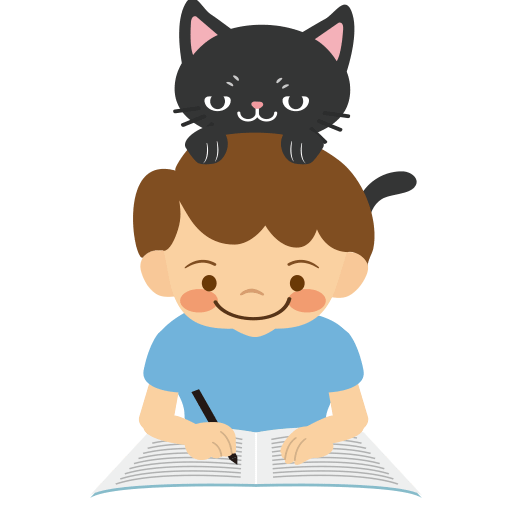
「読み継ぐなら本」「声や空気感は映像」「手軽に共有はデジタル」です。
タイプ別のメリット(向いている人)
① 本(書籍)
・読み返しやすく贈答に最適/長期保存に強い/手触りが記憶を呼び起こす
→ ご家族で回し読みしたい・記念品にしたい・落ち着いて読みたい方向け
② 映像(動画)
・声や表情まで残る/臨場感がある/式典・集まりで共有しやすい
→ 声や姿を残したい・上映の場がある・記念日で流したい方向け
③ デジタル(Web・データ)
・遠方とも共有しやすい/更新・検索が容易/費用調整がしやすい
→ 親族が遠方・スマホ閲覧中心・段階的に増補したい方向け
よくあるご質問
Q:写真が少なくても自分史は作れますか?
→ はい。文章中心や年表+出来事解説でも十分に読み応えが出ます。
Q:最初から1つに決めるべき?
→ いいえ。まずは本で形にし、後からデジタル化/映像化などの拡張もおすすめです。
Q:予算や期間が不安です。
→ 目的とボリュームを先に決めると無理なく調整可能。
最後に・・・
自分史は、形で選ぶものではなく、「誰に、どの瞬間に、どう届けたいか」で選ぶもの。
迷ったら小さく始めて、少しずつ広げるのがコツです。
すぎやま本制作では、本の制作を中心に、データ(電子ブック・動画)化のご相談も承っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。